私たちの体の中には、100兆個以上もの腸内細菌が棲みつき、まるで共生しているパートナーのように日々働いています。また「脳腸相関」といって、腸と脳が密接につながり、自律神経や感情にまで影響を与えていることが明らかになってきました。
腸の不調は便秘や下痢だけでなく、イライラや不安感、疲れやすさとしても表れます。
逆に腸の調子が整うと、自然と気持ちも軽やかになり、体全体が健やかに動き出すのです。
甘酒とオートミールで腸が変わった
私自身、長年便秘や下痢を繰り返し、腸が過敏で落ち着かない時期がありました。
そこで始めたのが、夜は米麹の甘酒を飲み、朝はオートミールを食べる習慣です。最初は半信半疑でしたが、続けていくうちに便通が安定し、下痢や便秘の頻度がぐっと減っていきました。腸が落ち着いてくると、不思議と気分も良くなります。
最近、背中の腫れで抗生物質を飲み続けたことがありました。その直後から腸の調子が一気に悪化。抗生物質は悪玉菌だけでなく善玉菌まで減らしてしまうためです。
しかし、薬をやめて甘酒とオートミールを続けると、1か月ほどで腸が回復。腸内細菌の力をあらためて感じた出来事でした。

妻の便秘にも変化が
実は妻も長年ひどい便秘に悩まされていました。数か月に一度は強い痛みに襲われ、緊急で病院で行かないといけないかもと思いつつヒーリングやお風呂に入り、何とか解消することもあります。そんな妻も、私と同じ習慣を取り入れるようになってから変化が訪れました。
「前よりもだいぶ楽になった。5割くらい改善した気がする」と口にするほど、便の質が変わってきたのです。
便秘に悩む方は多いですが、こうした小さな習慣の積み重ねで確実に体は変わっていくのだと実感しました。
腸が嗜好を変える?
さらに面白いことに、腸の状態が整うにつれて食べ物の好みまで変化してきました。
以前はポテトチップスやチョコレートが大好きでしたが、今は自然と饅頭や煎餅などが美味しく感じるように。
この嗜好の変化は、腸内細菌が自分たちの「餌」となる食べ物を欲し、私たちの嗜好に影響を与えている可能性があるといわれています。普段食べているものの中から該当する腸内細菌を育て、その腸内細菌がまた私たちの心や体に影響を返してくる、そんな循環もあるのです。

腸は「第二の脳」
人間の進化の過程では、脳よりも先に腸が誕生しました。それだけ腸の影響は大きく、「第二の脳」と呼ばれるのも納得です。腸を整えることは、自律神経や感情の安定につながる、心と体の要なのです。
今では「腸内細菌を摂る」よりも「腸内細菌を育てる」ことが大切だと考えられています。根野菜や、海藻、発酵食品、オリゴ糖や食物繊維など、腸の餌になる食品を積極的に摂ること腸内細菌の餌が減ると、
腸粘膜を食べていわいる「リーキーガット症候群」になることも
腸を整えることは、単なる便通改善だけでなく、心や自律神経の安定に直結しています。
私たち家族も体験を通して実感しました。
西宮市の当院では、自律神経の乱れや腸の不調に対して、気功整体を通じて回復をサポートしています。
腸内環境を整えたい方、自律神経を改善したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご予約・ご相談はこちらから
📞 電話:〈0798〉42-7182
💬 LINE相談も受付中!
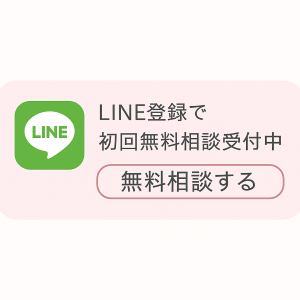
メールフォームからお問い合わせ





コメント